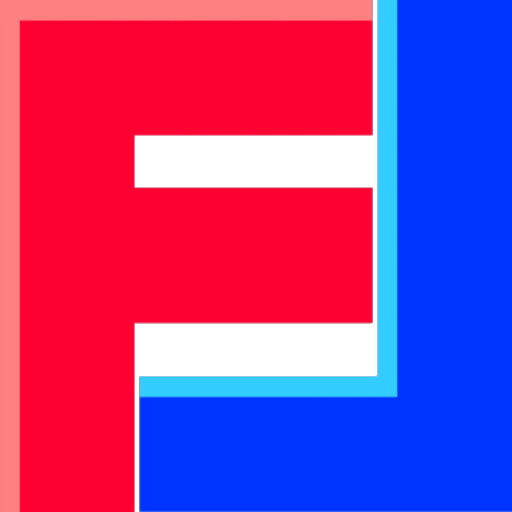なぜ、負けることが大切なのか

この記事は約 12
分で読めます
「私は負けん気が強いんです」
「ポジティブだから、全然大丈夫です」
「信じた事は絶対に曲げません!」
強い信念があるのは立派?
負けず嫌い、強気、勝気という人ほど、実は脆いものです。
価値観や考え方、人それぞれに意見の違いはあり、無意識に誰かと自分を比較するものです。
「どちらが上か」
「どちらが強いか」
「どちらが正しいか」
そしてその結果、勝者と敗者が生まれます。
それはさりげなくはっきりしたものではなくても、両者を2つに分けるのです。
リーダーと部下
権力者と民衆
上に立つものと従う者
など、様々な階級、区別、格差として存在します。
人類の歴史は、これらに集約されていると言っても過言ではありません。
だからこそ、自由や平等がスローガンになるのでしょう。
誰だって負けっぱなしや下手になるだけでは辛いですから、時には勝ちたいと思うのかも知れません。
虐げられた者たちの反逆も歴史の美談となっています。
強い信念があったから、最後には勝つことが出来た!やったぞ!!
正しさという劣等感
しかし、それが上手くいったとしても常に勝ち続けることも至難の業です。
上には上がいるものですし、そういうタイプを蹴散らさずにはいられない人も存在します。
「負けないぞ!」
「こっちだって、負けてたまるか!」
あるいは、
「頭にくるから無視してやる」
「相手にしないで遠ざけよう」
などの、拒絶的な対立。
好戦的であれば激しいやり取りになり、お互いにプライドやメンツを掛けて戦ったりもします。
政治家や評論家などは、世間体のポーズとしてやっている部分もあるかと思いますが、強く主張して相手を追い込むような姿も良く見かけます。
正しい事や権利を主張したいという想い。
いつの時代も、世のため人のために振りかざす「正義」に熱くなるのも分かります。
一見すると意志が強くて信念ある人物に見えるかもしれませんが、どうもそれだけではないような気がしないでしょうか。
さて、人に負けたくない人や自己主張する人に共通するものは何か?
その根底にあるのは劣等感です。
こういった人には、「自分は人よりも劣っている」というコンプレックスがあるのです。
それが疼くので、素直に負けを認められなかったり、相手に頭を下げることに抵抗感を持ちます。
「勝たなければ!」の裏にあるのは、負けることへの恐怖感や、人に劣って傷付いたり苦しむことを避けたいという弱さなのです。
(自分はバカにされるような人間だ…)→「バカにしやがって!」
(舐められるような人間だ…)→「舐めるな!」
(からかわれるような人間だ…)→「ふざけるな!」
そんな風にして、相手を鏡にして写し出すのです。
生い立ちの中で、認められている、信頼されている、肯定されている、愛されている、などが枯渇していたのでしょう。
幼いと自己中だったり、人を思いやることに欠けてきます。
負けん気はやはり、精神的な幼さの表れだと言えます。
心に余裕がある人
本当に自信を持っている人は、自分に危害が無ければ、相手を立てたり、認めたり、褒めたりすることが出来るでしょう。
相手が強い態度に出れば、さっと譲ることもできますし、勝ち負けなどというものに大したこだわりがありません。
多少の批判やお叱りを受けても素直に受け止めます。
心に余裕があるからです。
他人の評価や見返りなどに関心も無いですし、求められなければ多くを語ることもないはずです。
仮に良かれと思うことがあったとすれば、人知れず淡々と行っているだけでしょう。
能ある鷹は爪を隠す。
大賢は愚なるが如し。偽善者だ。バカだとなじられても意に介さない強さがあったり、人知れず誰かの役に立てることを喜びと感じていたりもします。
満たされているからこそ、他人にもそれを渡すことが出来るという循環です。何かを強く主張したいと思ったら
何かの投稿欄などを見ていると、時々激しい意見のやり取りを目にすることがあります。
両者一歩も譲らず、あの手この手でマウンティングをしあっているのですが、相手を追い込む言葉の巧みさに感心してしまいます。
それは、「どうしたら相手をギャフンと言わせられるか(勝てるか)」の努力の賜物です。
書いている人の精神状態が如実に表れていると思いますが、日常ではきっと我慢して耐えて、辛抱に辛抱を重ねているのかも知れません。
あそこまでのエネルギーの源泉となるものは、おそらく生活上のストレスではないでしょうか。
きっと悲しいことや苦しいこと(負けている事)が沢山あるのだと思います。
そのはけ口として、何かを訴えたくなるのは無理もありません。
しかし、その期待は大抵叶わないと思います。
ストレスというのは、誰かにぶつけてもすぐに溜まるものですし、根本から変化させないと堂々巡りになります。
何を訴えたところで、誰もがそれをあれこれと評価する余裕はなく、自分のことで精一杯です。
とかく、我慢を強いられてきた人ほど相談室で雄弁なのはとても自然な事です。
「話すことは“放す”こと」
「人は話すことで癒される」
そういった理論を目にすることもあります。
とにかく、何かを訴えたい欲求が治まらないとしたら、自分自身を観察してみると良いと思います。
「なぜ、こんなに頑張っているんだろう?」
「自分は、どんな人間だと思われたがっているのだろう?」
自覚できていれば、物事に対する捉え方も変化してきます。
泣けるライブ
以前、研修生の方に誘われて、あるミュージシャンのライブに行きました。

ギター一本でメッセージ性のある曲を歌う男性で、紹介されたときは、「始めて曲を聞いて泣けたミュージシャン」という事でした。
ライブハウスには、熱烈な常連のファンの方がいたりとなかなかの盛況ぶりです。
アコースティックギターを抱えて登場したその人物は、いかにもという感じのロングヘア―に長めの髭、奇抜な民族衣装風の服を身にまとっていました。
どこか70年代のヒッピーを彷彿とされる雰囲気です。
そして、表情はとても穏やかで人生経験豊富な賢者のようでした。
アルペジオで奏でる曲は、イメージしていた想像以上のメッセージ性があり、それをハイトーンボイスで叫ぶ様は、とても胸を打つものでした。
MCも魅力的で、彼が静かに語りだした途端に場の空気が変わります。
これまで旅した国の事、そこでの出会いとエピソード、どれもが彼ならではの表現で語られるのですが、それがとても興味深く、実に含蓄あるものでした。
ですが、感動はあっても泣くことは無いままにラストの曲を迎え、その曲名を告げるとファンの方が少し沸き立ちました。
代表曲なのかな?と思って聞いていると、開始数十秒で涙があふれてしまいました。
まるで一つの映画を観ているような感覚になる、美しいストーリーの曲だったのです。
曲を聞いて、あんなに泣けたことは生まれて初めてでした。
負けてこい
その場でCDを買い、余韻に浸る日々が続いていると、その出会いを結んでくれた研修生の方から再び連絡があり、地元で彼のコンサートを企画しているので参加しないか、とのお誘いを頂きました。
お言葉に甘えてお邪魔してみると、場所は地域の公民館で、準備は全て有志でまかなうというアットホームなものでした。
彼はこんな風に、呼ばれれば全国どこへでも出かけてコンサートを開くというスタイルで、口コミで活動が広がっているのです。
今回の主催者の息子さんが中学校でバスケットボール部に入っており、設営などの準備に部員7~8名も加わっていたのですが、休憩中の彼らに声を掛けていたミュージシャンが、ふと、少年たちの相談に乗るような流れになりました。
その部は地元でも強豪校で、決勝がかかっている重要な試合が近日に控えているが、その対戦相手がこれまで一度も勝てたことが無い優勝候補校だというのです。
コーチも檄を飛ばす熱血タイプで、それもプレッシャーなのだとか。
どんなアドバイスをするのか興味津々で聞いていると、彼が言ったことはなんと「負けてこい」というものでした。
部員たちはちょっと唖然としていますが、もっと驚いていたのは彼らの保護者達です。
3年生最後の決勝戦。どうしても勝たしてやりたいと言うのが親心でしょう。
しかし、それに対して彼は続けたのです。
僕は今まで、100カ国以上を旅してきた。
異国では何もかもが違う価値観や習慣の中で、差別を受けたり騙されたりして、負けることを強いられてきた。しかし、そうやって負ければ負けるほど人生が豊かになることを知った。
「負ける」ことは自分を成長させる最大の「チャンス」だ。
常に勝ちつづけてきた優等生は、たった一回の敗北で自殺してしまうこともある。
負け続けたものは、同じ痛みをもつ者たちへ手をさしのべることができる。
自分の弱さをさらけ出し、補い合い、分かち合い、助け合うところから、「競争から共存」への未来ははじまる。
実に重みのあるアドバイスであり、見事なパラドックス介入だと思いました。
流石です。
コミュニケーションの達人
その日、すでにファンになっていた私は、二度目のライブをしみじみ味わっていると、途中のMCで彼らについての話題になりました。
そして、贈りたい歌があるといって披露されたのが、敗北をテーマにした曲でした。
メッセージが詰まった、バスケ少年たちにぴったりの曲です。
勝つことだけを強いられて、そうなることだけを求めてきた部員たちは、それをじっと聞いていました。
恐らく、何人かは涙を浮かべていたように思います。
その後の打ち上げにも是非ということなので喜んで参加しましたが、つくづく旅から学んだ実学の先生だという感想です。
言葉に重みと説得力があり、何よりも自然体で魅力的な人でした。
旅とは、出会いであり交流です。
すなわち、彼はコミュニケーションにおける国際的な達人だと言えるでしょう。
そして、同時に負けることの達人でもあるのです。
彼の言葉を借りれば、コミュニケーションとは相手に負ける事だと言えるのかも知れません。後日、バスケの試合の結果が報告されました。
残念なことに、勝ってしまったそうです。
記事を書いた人 Wrote this article
Kondo
短期間で改善を起こす、ブリーフ・サイコセラピー派の心理師。 あらゆる問題の解決事例を持ち、超合理的に結果に導く。 臨床から産業、教育分野まで、幅広い実践経験を持つ。 専門家からの相談を受けるマスター・カウンセラーである。