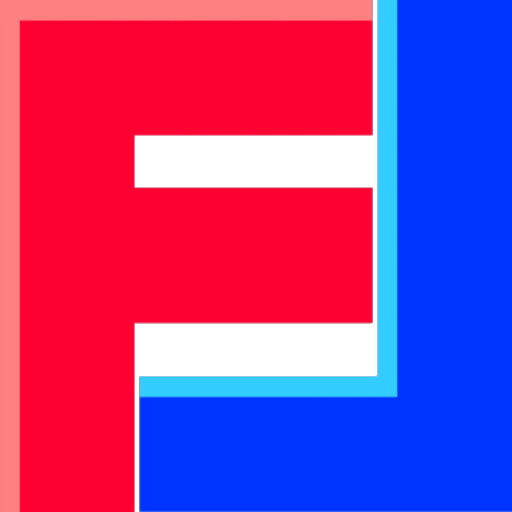オタク、ニート 天才論

この記事は約 9
分で読めます
目次
Outline
Outline
オタク、ニート、不登校、問題児は天才です。
彼らには人とは違った能力が備わっています。突出した知識や関心、熱意と独創的な感性。馴れ合いで群れることなく、自らが信じた確固たる人生を選んでいます。
実際に、社会的に成功を収めた人達には、こういったタイプが数多く存在します。

かと言って、社会性がない人というのは何をしでかすかわかりませんし、人によっては排他的だったり批判的だったりして他人との擦り合わせが難しいのも事実です。
そういったタイプが身近にいると、付き合うのが非常に疲れます。
家族や子供だったら尚更で、毎日が混乱の連続にもなるでしょう。
確かに、平均的で協調性があり、明るく朗らかで運動も勉強も熱心で…、それはそれでとても素晴らしい個性です。
しかし、それだけが評価され求められる社会というのはどうでしょうか?
ひとつの価値基準だけで人間を量るようで、少し偏りを感じてしまいます。

実際、カウンセリングを受けに来られる方の中に、こういった傾向を持つ方はとても多いです。
朝から深夜までオンラインゲームをする少年。
SNSやネット映像を一時も切らない少女。
寝ても覚めてもアニメ(アイドル、サブカルチャー)に没頭する青年。
コスプレや奇抜なファッション(髪型、メイク等)に執心する少女。
趣味の範疇ならいざ知らず、依存、中毒のレベルで学業や生活に支障をきたすとなれば周囲も困り果ててしまうでしょう。
当然、「問題のある子(人物)」として意味付けられます。
何かに集中し没頭することは素晴らしい部分もありますが、それが非生産的だったり、人に役立つものでないと認められずらいのです。

そして、レッテルを貼られると次第にそれに当人も拘束されてしまいます。
「どうせ誰にも理解されない…」
「自分は厄介者なんだ…」
時には追い詰められて消えてしまいたくもなるでしょう。
そういった彼らのレッテルを覆すのが我々の役目です。
オンラインゲームのポジティブな側面は何か?
SNSやネット映像の知識を何かに活かせないか?
アニメやアイドルへの熱意がビジネスにならないか?
独創的な美意識を作品として発表できないか?
これをリフレーミング(枠組みを替える)と言います。
ポイントは2つあって、第一に面接者があらゆる価値観から自由になれている(その準備がある)事。
Aは良いがBは悪いなどといった、主観的な思考では新しい発見が困難になります。
もう一つが、熱量の一致です。
相手は、ある意味その道のプロであり熟練者です。誰よりもそのことに詳しいですし、並々ならぬこだわりや主張を持っています。
ですから、表面的な態度で「面白そうなゲームだね」とか、「可愛いキャラクターですね」などと言っても、抵抗を感じてしまうのです。
『ふん!お前ごときに何が分かる!』
情熱を傾けるものがあれば、誰だってそうだと思います。
素人に、分かったような口を利いてもらいたくありません。
私は音楽が趣味なのですが、その中でも70年代から80年代のアメリカとヨーロッパのロックが好きです。

ある時、趣味を聞かれたので、「音楽鑑賞です」と答えると、「ジャンルは何ですか?」と聞かれました。もしかすると、音楽がお好きなのかと思い、「少し古い時代のロックが好きです」と答えました。
すると、
「ああ!アルフィーとかですか?」
…… 別にいいんです。アルフィーでも。
一流ミュージシャンですし、嫌いじゃありません。
しかし、何というか、“浅さ”とか“ピントの違い”を感じてしまいました。
一般の誰もが知っているロックバンド=アルフィー。
この時点で、この方とのロック談議は難しいです。
もちろん、相手もそれを望んではいないと思いますが、他の話題の方が良いかも知れません。
例えるなら、インドカレーのスパイスについて語り合おうとしたら、相手が「ボンカレー」を推してくる、みたいな感覚です。
いや、美味しいのは事実なんです。
アルフィーは他に類のないモンスターバンドですし、ボンカレーは国民的な商品です。でも、偉そうなことを言うわけではありませんが、大衆的過ぎてマニアックじゃないんです。

オタク気質というのは、そういったポピュラーなものを避けたり嫌う傾向があります。
アニオタに「ドラえもん」や「クレヨンしんちゃん」は意外と刺さらないでしょう。
もし大衆的なものだけに満足できていたら、大多数の一員として安定出来ていたかも知れません。
さて、そういったマニアックな彼らと熱量を一致させるのですが、それにはコツが必要です。
知識的に追い付ける訳もなく、知ったかぶりは尚更良くありません。
考え方としては、一人の人間がそれほどまでに時間や労力を費やすものに無駄なものや下らないものは存在しないということです。
ですから、本気になって真剣に興味と関心を持って聴くのです。
すると、本当に今まで知らなかったことが悔やまれる程に価値あるものだと気付かされます。
そういう視点は、とても重要だと言えます。
社会は、理解できないもの、異質なものを排除しがちです。
スクールカーストという言葉もありますが、幼い子供は特にその傾向があると思います。
「あの子のランドセルは変わった色だ」
みたいなことですら判断の対象となりますし、ジャニーズの話題で盛り上がるクラスメイトの中で一人だけ太宰治を読んでいたりすれば、きっと悪目立ちするでしょう。
人は、やはり似た者同士で集まります。
態度一つでも、
「こいつ笑わないな」
「会話が続かないな」
「からみづらいな」
といった関わり方にもジャッジが入り、
「変なやつ」
「変わり者」
「ヤバイ」
「キモイ」
などと、やがて人格にまで影響を及ぼします。
幼いので、差別や偏見の意識さえおぼつかないかも知れません。
そのような集団意識に何とか紛れようとしても、天才には常に居場所の無さが付きまといます。
優れた能力を持つ者ほど、一般社会では馴染み辛く孤立しがちなのです。
でもご安心ください。世界は変動し続けています。
eスポーツの世界チャンピオンは引き籠りで、有名なユーチューバーは不登校児で、著名なアニメクリエイターはいじめられっ子でした。
その他にも、元ニートのアスリート、少年院出のアイドル、自殺未遂のミュージシャンなど、数えたらきりがありません。
ギーク(geek)とナード(nerd) という英語は、日本語の「オタク」を意味しますが、ギークと呼ばれる人たちの6~7割の人々は、それに誇りを感じていると答えています。
あるニートの男性が、数年ぶりにメールをくれました。
添付の画像ファイルを開くと、彼がスポーツカーの前で変なポーズを決めていました。
「働きたくない」
「人に使われたくない」
「楽して生きていきたい」
そんな人だったのに…。

けしからん!
個人投資家として成功するなんて!
…もっと詳しくやり方を聞いておけばよかった。
記事を書いた人 Wrote this article
Kondo
短期間で改善を起こす、ブリーフ・サイコセラピー派の心理師。 あらゆる問題の解決事例を持ち、超合理的に結果に導く。 臨床から産業、教育分野まで、幅広い実践経験を持つ。 専門家からの相談を受けるマスター・カウンセラーである。